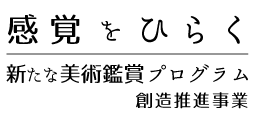トーク&ディスカッション 「美術館のあたりまえって?」実施報告
- 開催日
- 2019年3月12日(火)14:00~16:00
- 講師
-
高嶺格(美術家・秋田公立美術大学教授)
光島貴之(美術家・鍼灸師)
広瀬浩二郎(国立民族学博物館准教授)
- 会場
- 京都国立近代美術館 1階講堂
- イベント詳細
- トーク&ディスカッション 「美術館のあたりまえって?」
本イベントは、「感覚をひらく」の2年間の事業の締めくくりとして実施した。本事業がどのような理念で新たな鑑賞プログラム構築を進めていくべきか、もういちど原点に立ち返って考える機会を持つこと、そして視覚障害者と共働するうえでの美術館としての心構えについて、高嶺氏、光島氏、広瀬氏のそれぞれの話からヒントを得、会場とも考えを共有することを目的に開催したものである。
高嶺氏トーク

2008年にせんだいメディアテーク(以下、仙台)での「大きな休息 明日のためのガーデニング1095m2」展と、2014年の秋田県立美術館(以下、秋田)での「手さぐる」展について触れながら、トークは進行した。2つの展覧会に共通するのは「廃材(不要とされたもの)によって展示を構成したこと」、「視覚障害者のガイドによって会場を巡ること」であった。会場には何の意味もなさない空間を設えようと試み、仙台では解体された家の廃材や不要になった着物など、従来は美術館から"はじき出される"ものを集め、それら全てが等価であると見えるように会場を構成したという。
さらに会場内に置かれたものについて話をしながら「意味」を付与・生成してみるという仕掛けを考えた際、案内役として、同じく近代的な美術館のシステムから"はじき出された"存在として、視覚障害者が頭に浮かんできたと話す。このように2つの展覧会は、歴史的に価値付けされたものを展示し視覚的に理解する場所という美術館のシステムから最も遠い所にある「廃材」と「視覚障害者」という存在をあえて持ち込むことで、社会に対する異議申し立てをした試みであったと振り返った。
また高嶺氏は、来場者が展示をどのように経験するか、その反応にも気を配っていたという。すると、ガイドがわざと誤った認識をしているフリをしても、健常者は「気を遣って」間違いを指摘できないという状況がしばしば起きていたことを目の当たりにしたそうだ。そうした場面に何度も立ち会うにつれ、運転中にカーブミラーに車が映っていないと認識していても、「本当は存在しているのでは?」と、自身の固定観念が揺らぐような不思議な感覚に襲われたという自身のエピソードも語った。
ディスカッション
続いて、光島貴之氏と広瀬浩二郎氏を交え、それぞれの立場から「障害者と共働すること」などをめぐる考えをお話しいただいた。

冒頭に光島氏が、視覚障害者が美術鑑賞に関わるいくつかのケースについて言及した(①見えない人と見える人が言葉で鑑賞する、②鑑賞に対する晴眼者の意識を刺激するために、作家が見えない人をアテンドとして"利用"して鑑賞を行う、③見えない人がナビゲーターとなり、従来とは異なる方法としての「さわる鑑賞」を提案する)。続いて仙台でのアテンドとの比較事例として、同氏が2017年夏に京都芸術センターで展示されたオ・インファン《死角地帯探し》でのドーセント(案内役)に関わった経験を紹介した。本作は、来場者がドーセントに主体的に声を掛けた場合のみ案内を受けられることなど高嶺氏の作品との相違点はあったものの、いずれも「自分自身が作品の中に入り込んでいく」という興味深い体験であったと振り返った。
この話を聞いていた高嶺氏は、自身の展覧会の終了後、「自分は視覚障害者を搾取しているのではないか」という罪悪感や申し訳なさに駆られたと当時の心境を吐露した。私たちはそれぞれが"うまくいかないこと"を抱えており、そうした意味では社会の中に障害の有無を示す明確な線引きは存在せず、皆が障害のグラデーションの中のどこかに位置すると考えている。しかし仙台・秋田の展示において「見えない」ことを際立たせる行為は、線引きをするという一般的な認識を利用していることに他ならない。自分は嘘をついているのではないかという思いが拭い去れないのだと、高嶺氏は語った。これに対して光島氏は、「自分は楽しんで関わっていたし、搾取されているとは全く感じなかった」と明言した。広瀬氏は高嶺氏の率直な思いを受け止めながらも「どうぞ搾取してください」と朗々と述べ、「飯を食い、お酒を飲んで、搾取する」という一句を披露すると、会場は笑いに包まれた。
一方で、「見えない人は自分とは圧倒的に違う能力を持っている」という高嶺氏の考えに対しては、光島・広瀬両氏がそれぞれ「目が見えない人は超能力を持ったスーパーマンではない」とコメント。とはいえ光島氏は、長年美術鑑賞に関わる中で、晴眼者との違いを際立たせたり障害者を持ち上げたりすることによって、美術鑑賞において気づきが大きくなったり「面白くなる」ことがあることも分かってきたという。広瀬氏は、見えない人と見える人の共働の歴史の中で特筆すべき事例として、1988年に晴眼者からの発案で始まったダイアログ・イン・ザ・ダークに言及し、高嶺氏の活動は、「晴眼者が既存の価値観を疑うために発信する」という点で同じ流れの中に位置づけられると述べた。さらに、前者は非日常(暗闇)の中での体験が日常(明るいところ)にどれほど影響を与え得るのかという点が懸念されるのに対し、高嶺氏の展覧会は自然なかたちで見えない方に案内されるという仕組みになっており、より先進的だと評価した。晴眼者がこうした場を主体的に設けているという点でも画期的であり、今後もぜひ継続して取り組んでほしいと高嶺氏にエールを送った。
さらに、本事業が3年目に視覚障害者や作家と共働したプログラム構築を検討していることを踏まえて、「感覚をひらく」の実行委員という立場からも見解を述べた。一点目は、視覚障害者もぜひ参加したいと思えるプログラムにすること。見える・見えないにかかわらず、だれもが楽しめ、気づきを得られる内容を目指すべきであり、運営側の心構えとして、少数派である障害者への細やかな配慮も欠かせない。もう一点は実施の枠組みに関して、アーティスト(Artist)、視覚障害者(Blind person)、学芸員(Curator)の三者(ABC)が共働することの意義である。ABまたはBCの共働関係は前例があるものの、ABCがそろってプログラムを構築するという事例は少ない。そこで「感覚をひらく」ではぜひともABCが知恵を出し合いながら、オリジナリティのあるプログラムを創造したいと、期待感を込めて語った。
今回のトークでは、「感覚をひらく」の今後について、高嶺氏・光島氏からの具体的な助言を引き出すことができず残念であった。しかし、展覧会を作るという方法によって美術館という制度自体に疑問を投げかけ、そこを訪れる人と共に考えようとする高嶺氏の真摯な姿勢には、利用者と共に美術鑑賞の概念を拡げようという本事業と通じるものがあったことは、共有されたのではないだろうか。また、障害のある方の力を借りることへの罪悪感や葛藤を常に抱いているという作家としての率直な思いと、それに対して光島氏、広瀬氏の2名の障害当事者から前向きな発言があったことも興味深い。広瀬氏からABCの共働について言及もあったように、本事業では今後、さまざまな人が集まりそれぞれの経験や感性を生かして新しい美術鑑賞のありかたを模索していく。その中で美術館として考えが及ばない/経験が至らない部分は、視覚障害のある方やアーティストや専門家など、外にいる人たちと積極的に対話をしながら、最適な方法を探っていきたいと考えている。
(文責:松山沙樹)
<参加者アンケートから(抜粋)>
視覚的に経験される世界(あるいはその一部としての芸術作品)と非視覚的に経験される世界を比較し、気づくというのは、それまでの概念にしばられた知覚から離れた美的経験になりうるものだと感じました。一方で、見える人と見えない人が、言語によってお互いの経験を交換する(意見を交わす)場合、言語が持つ意味(概念)は見える人によって経験された世界の記述であることに大きく制約されそうです。非視覚的美的経験を作品において実現するためには、かなり仕掛に工夫が必要であり、高嶺氏やオ氏の作品をその実例の一つとして拝見しました。高嶺氏が今回紹介された作品制作において敢えて意味を持たせなかったというのは、そして案内係の人に詳しい説明をしなかったのは、視覚にとらわれた経験を改めて外界に向けて開くという意味において、有効だったのではないかと考えます。
(50代・男性)
"見える"ことが"健常"と考えることから"見えない人"へ何かしてあげなければならないと思うことが当たり前のようである中、"見えない人"にアテンドしてもらう逆転の鑑賞は非常に興味深い。(芸術センターで、"声を掛ける"ことから"始める"というこだわりは、鑑賞者の逆転の発想への問い掛けであるように思える)暗室内での鑑賞は"見える"からこそ感じる恐怖があり、"見える不自由(?)"を体感することが、逆転の発想を自由に行き来できる鍵になるのかな、と思えました。"見えない人の気持ちがわかりました"は、発想が逆転していないですね。
(40代・女性)
ディスカッションが行き先の見えないようなトーク内容だったので、いくらか話の深まりに欠けてしまったように感じました。今回の表題になっているような「美術館のあたりまえって?」の内容を深められる対話活動になっていたら、更におもしろい話が聞けたのではないかと思います。物足りないなと思うこともありましたが、全体としてはとても貴重なお話が聞くことができました。
(20代・男性)
視覚障害者と健常者の「つながり方」はたくさんあるが、あえて美術館という場やアートという媒体をもちいることでどのような相互理解が得られるのか、その意図がよくわかった。一方で、質問でも出ていたように、美術館以外の場で両者がどのようなことをできるのか、つまりより広いフィールドでお互いの感覚をひらくような経験が必要だと思う。
(20代・男性)